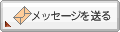2005年09月17日
琉球箏とは何ぞや その4 ~曲と歴史~
琉球箏はどんな曲を演奏するのか。
和箏の代表的な曲に「六段」がありますが、琉球箏曲でも「六段」があるのです!
教室に入門する前、見学に行った際このことを知って、軽くショックを受けました
(いい意味で)。
その時私は民謡と古典の違いもわかっておらず、
「箏でもああいう感じの曲をやるのだろう」と思っていました。
先生に「以前山田流を習っていた」と言ったら、「沖縄にも六段があるよ」と弾いてくれたのです。
感想は「なんか変な感じ」(失礼)。
弾く弦は同じなのだけど、音階は低くリズムがゆったりしているため、
「六段」だとすぐには分からない。
それから休符が入るところが時々違うようで、「えーっなんでここで止まるの??」
ということがたまにある。それがなんともムズムズするのです。
「六段」の話は、こんな思い出から個人的に思い入れがあるので(^^;)、
別の記事で書きたいと思います。
さて琉球箏曲の説明に入る前に、琉球箏の歴史の話をさらっとさせていただきます。
和箏の代表的な曲に「六段」がありますが、琉球箏曲でも「六段」があるのです!
教室に入門する前、見学に行った際このことを知って、軽くショックを受けました
(いい意味で)。
その時私は民謡と古典の違いもわかっておらず、
「箏でもああいう感じの曲をやるのだろう」と思っていました。
先生に「以前山田流を習っていた」と言ったら、「沖縄にも六段があるよ」と弾いてくれたのです。
感想は「なんか変な感じ」(失礼)。
弾く弦は同じなのだけど、音階は低くリズムがゆったりしているため、
「六段」だとすぐには分からない。
それから休符が入るところが時々違うようで、「えーっなんでここで止まるの??」
ということがたまにある。それがなんともムズムズするのです。
「六段」の話は、こんな思い出から個人的に思い入れがあるので(^^;)、
別の記事で書きたいと思います。
さて琉球箏曲の説明に入る前に、琉球箏の歴史の話をさらっとさせていただきます。
18世紀はじめ頃、ある薩摩藩士が京都に赴き、八橋検校の弟子に箏曲を学び、国へ帰った。
その薩摩藩士に、琉球から王命を受けてある役人が赴き、箏曲を学んで国へ伝えた。
八橋検校の死後20年足らずで琉球に箏曲が伝わったことになる。
19世紀はじめ頃、三線とともに宮廷楽器として使用されたという文献があり、
この頃琉球箏曲が創始したと考えられる。
つまり、琉球箏は 京都 → 薩摩 → 琉球 と伝わったのです。
同じ沖縄の楽器、三線が 琉球 → 薩摩 → 本土
と伝わって三味線になったのと全く逆になりますね。
※箏の沖縄伝来には諸説あるようですが、今回は「沖縄箏曲工工四」から抜粋したものを掲載。
(余談ですが、箏の楽譜も工工四といいます。記号に工工四を使うわけではないのですが)
琉球箏曲には、大きく分けて2つのパターンがあります。
1.本土伝来の楽曲
2.沖縄創始の琉球箏曲
まず 1.本土伝来の楽曲 から。
薩摩から箏曲を学んだ者がいくつか楽曲を持ち帰りました。
これが今も残り「菅攪(すががき)」7曲と「歌物」3曲になります。
菅攪7曲は歌がない器楽曲で、これ以外の曲は歌があります。
菅攪は、沖縄方言では「スィガガチ」と呼び、段物と言われることもあります。
「瀧落」「地」「江戸」「拍子」「佐武也(さんや)」「六段」「七段」の7曲です。
歌物は、「船頭節」「対馬節」「源氏節」の3曲です。
歴史にもあるように、琉球箏曲は八橋流の流れだと考えられています。
八橋流は、生田流・山田流などの祖になった流派で、
もともとの八橋流は現在ほとんど残っていないといいます。
音楽学者・田辺尚雄氏は「琉球箏の形も爪も八橋流のままだ。
日本本土で亡びたものが琉球に残っているという点において、
音楽史上非常に貴重なる材料だ」と語っております。
日本の古い箏曲の形が、本土から遠い沖縄に生きているというのは、なんとも不思議なことです。
2.沖縄創始の琉球箏曲
八橋流伝来の曲をベースに、沖縄音楽に合わせ奏法などに改良を加え、
やがて三線の伴奏楽器として発展していきました。
踊りの地謡などで三線や笛、太鼓、胡弓と合奏したり、
三線1本と筝1本というセットで独唄するという形態もあります。
唄は三線奏者が務め、箏奏者は基本的に歌いません。
古典音楽の工工四があるのは200曲余りとのこと。
これらは宮廷音楽が発祥ですが、現在は「安里屋ユンタ」などの民謡、
「花」など新しい曲も演奏しています。
古典曲はこちらで聴くことができます↓
http://www.wonder-okinawa.jp/014/4inst/index3.html
長々と書いてしまいましたが、ご理解いただけましたでしょうか…。
その薩摩藩士に、琉球から王命を受けてある役人が赴き、箏曲を学んで国へ伝えた。
八橋検校の死後20年足らずで琉球に箏曲が伝わったことになる。
19世紀はじめ頃、三線とともに宮廷楽器として使用されたという文献があり、
この頃琉球箏曲が創始したと考えられる。
つまり、琉球箏は 京都 → 薩摩 → 琉球 と伝わったのです。
同じ沖縄の楽器、三線が 琉球 → 薩摩 → 本土
と伝わって三味線になったのと全く逆になりますね。
※箏の沖縄伝来には諸説あるようですが、今回は「沖縄箏曲工工四」から抜粋したものを掲載。
(余談ですが、箏の楽譜も工工四といいます。記号に工工四を使うわけではないのですが)
琉球箏曲には、大きく分けて2つのパターンがあります。
1.本土伝来の楽曲
2.沖縄創始の琉球箏曲
まず 1.本土伝来の楽曲 から。
薩摩から箏曲を学んだ者がいくつか楽曲を持ち帰りました。
これが今も残り「菅攪(すががき)」7曲と「歌物」3曲になります。
菅攪7曲は歌がない器楽曲で、これ以外の曲は歌があります。
菅攪は、沖縄方言では「スィガガチ」と呼び、段物と言われることもあります。
「瀧落」「地」「江戸」「拍子」「佐武也(さんや)」「六段」「七段」の7曲です。
歌物は、「船頭節」「対馬節」「源氏節」の3曲です。
歴史にもあるように、琉球箏曲は八橋流の流れだと考えられています。
八橋流は、生田流・山田流などの祖になった流派で、
もともとの八橋流は現在ほとんど残っていないといいます。
音楽学者・田辺尚雄氏は「琉球箏の形も爪も八橋流のままだ。
日本本土で亡びたものが琉球に残っているという点において、
音楽史上非常に貴重なる材料だ」と語っております。
日本の古い箏曲の形が、本土から遠い沖縄に生きているというのは、なんとも不思議なことです。
2.沖縄創始の琉球箏曲
八橋流伝来の曲をベースに、沖縄音楽に合わせ奏法などに改良を加え、
やがて三線の伴奏楽器として発展していきました。
踊りの地謡などで三線や笛、太鼓、胡弓と合奏したり、
三線1本と筝1本というセットで独唄するという形態もあります。
唄は三線奏者が務め、箏奏者は基本的に歌いません。
古典音楽の工工四があるのは200曲余りとのこと。
これらは宮廷音楽が発祥ですが、現在は「安里屋ユンタ」などの民謡、
「花」など新しい曲も演奏しています。
古典曲はこちらで聴くことができます↓
http://www.wonder-okinawa.jp/014/4inst/index3.html
長々と書いてしまいましたが、ご理解いただけましたでしょうか…。
Posted by きょう at 23:00│Comments(0)
│琉球箏マメ知識