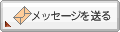2005年11月01日
コンクール体験記 その6
本番スタート。
舞台の袖から出てまず一礼。
箏の前まで進み出て正座。
箏と自分の間にこぶし2個分のスペースを空けるのがポイント。
座ってまたお辞儀。箏の直前まで膝と両手でにじり寄って、位置を調整。
この間、客席の方は一切見ませんでした。
審査員の姿を確認したら、舞い上がってどうしよもなくなるだろうから。
手を箏の上に構える。
舞台の袖から出てまず一礼。
箏の前まで進み出て正座。
箏と自分の間にこぶし2個分のスペースを空けるのがポイント。
座ってまたお辞儀。箏の直前まで膝と両手でにじり寄って、位置を調整。
この間、客席の方は一切見ませんでした。
審査員の姿を確認したら、舞い上がってどうしよもなくなるだろうから。
手を箏の上に構える。
1曲目は「瀧落菅攪」。歌のない器楽曲。
2分ぐらいの短い曲ですが、左手の奏法が頻繁にあって、
これをもれなくやるのはなかなか難しい。
ゆったりとしたテンポを一定にキープしないといけなくて、これもやっかい。
緊張すると走りやすいので注意する。
常々「走るな~」「抑えろ~」と自分に言い聞かせて弾いていたので、
その点は成果が出ていた(ような気がする)。
最後のほうで、左手で3回弦をたたくところを1回にしてしまい、「やべっ」と焦ったが、
それ以外は無難にこなせた(と思う)。
本当の本番直前に舞台へ呼ばれたので、緊張を意識せずにスタートを切れました。
でも手が重くなって思うとおりに動いてくれず、
ドキドキ感はなくても緊張はしていたのでしょう。
2曲目は「すき節」。1分ほどの短い、歌い弾きの曲。
「♪しっ つぃしつぃがぁーーー♪」 あー自分でも声震えてるの分かるー。
もっと声出ないかな、リカバーしたいなぁ、と思っているうち歌の部分終了。
まだ後奏弾いているのに、舞台袖で先生が「あ~よかった~!」と目をぎゅっとつぶって、
うずくまったのが見えました。体は緊張してても、意識は結構冷静なんだなぁ。
座ったまま少し後ろに下がりお辞儀。立って舞台袖へ歩く。
先生方が「上等!上等!」「合格よ!」と声をかけてくれる。
まだ体がふわふわした感じで、引っ張られるまま控え室に戻りました。
合否は、部門毎(箏の新人部門、三線の優秀部門、など)にその試験終了後、
数時間で発表されます。
合格者の番号と名前は、会場ロビーに張り出されるのです。
それまでお茶したり、買い物したりして過ごしました。
崇元寺近くの「またよし楽器店」にいたとき、
ひと足先に戻った先生から「弟子、全員合格」と電話が入りました。
あれっ?もっとうれしいものだと思ったのに、意外に冷静に受け止めています。
「やり終えた」という開放感のほうが大きくて、合格の実感が湧かないのでしょうか。
会場に戻り、模造紙に手書きされた自分の名前を見ます。
書いてありました。でも実感湧かず…
その7に続く。
2分ぐらいの短い曲ですが、左手の奏法が頻繁にあって、
これをもれなくやるのはなかなか難しい。
ゆったりとしたテンポを一定にキープしないといけなくて、これもやっかい。
緊張すると走りやすいので注意する。
常々「走るな~」「抑えろ~」と自分に言い聞かせて弾いていたので、
その点は成果が出ていた(ような気がする)。
最後のほうで、左手で3回弦をたたくところを1回にしてしまい、「やべっ」と焦ったが、
それ以外は無難にこなせた(と思う)。
本当の本番直前に舞台へ呼ばれたので、緊張を意識せずにスタートを切れました。
でも手が重くなって思うとおりに動いてくれず、
ドキドキ感はなくても緊張はしていたのでしょう。
2曲目は「すき節」。1分ほどの短い、歌い弾きの曲。
「♪しっ つぃしつぃがぁーーー♪」 あー自分でも声震えてるの分かるー。
もっと声出ないかな、リカバーしたいなぁ、と思っているうち歌の部分終了。
まだ後奏弾いているのに、舞台袖で先生が「あ~よかった~!」と目をぎゅっとつぶって、
うずくまったのが見えました。体は緊張してても、意識は結構冷静なんだなぁ。
座ったまま少し後ろに下がりお辞儀。立って舞台袖へ歩く。
先生方が「上等!上等!」「合格よ!」と声をかけてくれる。
まだ体がふわふわした感じで、引っ張られるまま控え室に戻りました。
合否は、部門毎(箏の新人部門、三線の優秀部門、など)にその試験終了後、
数時間で発表されます。
合格者の番号と名前は、会場ロビーに張り出されるのです。
それまでお茶したり、買い物したりして過ごしました。
崇元寺近くの「またよし楽器店」にいたとき、
ひと足先に戻った先生から「弟子、全員合格」と電話が入りました。
あれっ?もっとうれしいものだと思ったのに、意外に冷静に受け止めています。
「やり終えた」という開放感のほうが大きくて、合格の実感が湧かないのでしょうか。
会場に戻り、模造紙に手書きされた自分の名前を見ます。
書いてありました。でも実感湧かず…
その7に続く。
Posted by きょう at 23:00│Comments(0)
│琉球箏マメ知識